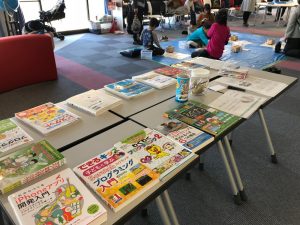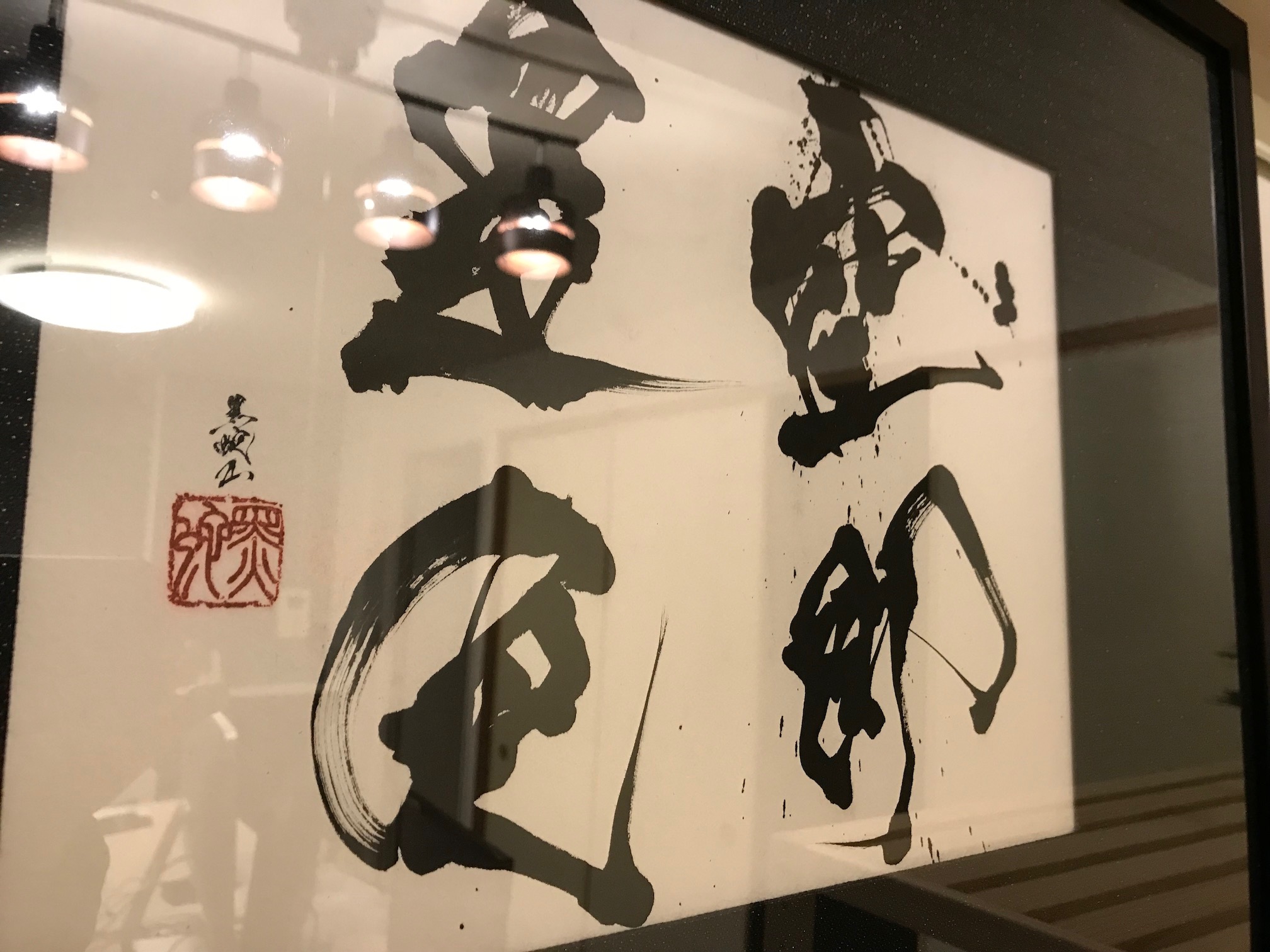7月にAmwayのディストリビュータ登録してから、書こうと思い続けて、はや3ヶ月…。いちおう、所信表明のようなものを(1年後に読み返した自分がどう思うかな?)。
薄利多売を是とする小売業のシステムに関わらせて貰って、もう10年が経ちます。グランドデザインをする立場にいないとはいえ、流通業というものが今後どんな風に変わっていくのか、ということには常に一定の興味があります。
効率化がとてつもなく進んで、すごく安い値段で食品や日用品が手に入るようになった反対側で起きていることは何なのかというと、一番わかりやすいのは経営効率の悪い個人商店が潰れていくことです。「経営効率」という一軸だけで捉える限り、世の中は徐々に良くなってきているんですが、その「効率の悪い」部分は本当に無駄だったのでしょうか?例えば、店長の道楽で仕入れた変な商品が、新しい食文化に触れるチャンスを地域に提供していたり、御用聞きのバイトが道草して、どこかの誰かの悩み相談にのっていたり。…やっぱり無駄かな(^^;
でも、そもそも豊かさって余剰や余白のことです。
Amwayの解説で「流通の無駄を省くから原価率の高い(=良い)ものが届く」って言われることが、ありますが、自分の肌感覚としては、もう時代は逆転しています。ネットワーク・ビジネスという仕組みを抱えている分、ちょっと高い。だけど、その「ネットワーク」の副産物に目を向けるべきと考えました。「仲間を作る」というアクションに上手にインセンティブが乗ります。無縁社会と揶揄される日本の社会構造に対する一定の処方箋になるのではないでしょうか。セカンドクリエイタという言葉がありますが、人間誰しもがそんなに上手に「自己表現」ができるものではないと思います。表現が苦手な人間でも、隣の人に話しかけるモチベーションがこの仕組みから提供されることが面白い点だと思います。
包丁とかナイフを例にあげるまでもなく、どんなシステムでも悪意を持って利用すれば、他者を傷つける結果につながることは起こり得ます。要は、使い方次第。過去に酷い使い方をした人たちが居たからネガティブなイメージが蔓延していますが、もともとのシステムに悪意はありません(規約を隅々まで読めば伝わると思います)。
使い方に気をつける、ということでは、自分は以下の2つを原則としていきたいところです。
- お勧めをする、情報を伝える、お願いは絶対しない
- 他の製品やビジネスを批判しない
チャンスを掴んで一攫千金!なイメージのビジネスではなく、どちらかというとコツコツすすめるタイプのビジネスだと認識しています。「自分の隣に居る人に情報を正しく伝える」ことが自分はとても苦手だったんだな、と再確認できたことが最初の収穫だと思います。